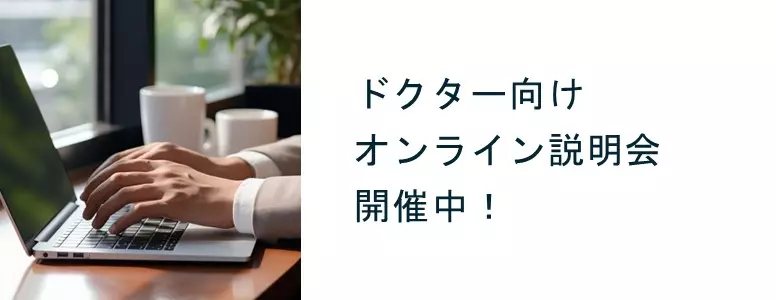第7回 子どもの適切なかかり方

小高 水曜日のこの時間は「健康のつボ!~病院の上手な使い方」、いざという時に頼っていく病院とはどういう付き合い方をしていけば良いのでしょうか。一宮西病院 事務長の前田 昌亮さんにお話をうかがいます。
大前さん先週、このコーナーでは前田さんに救急外来について教えていただいたんですよ。で、救急車を呼ぶか、病院へ行くか迷うときってありますよね。そういうときは、まず救急あんしんセンター「#7119」にかけてくださいということなんです。電話先にはドクターや看護師さんがいらっしゃって、病院へ行けばいいのか、それとも救急車を呼ぶべきか教えてくれるんです。
大前 これ本当に、子どもが今1歳半で、これ思うことめっちゃあるんですよ。ほんとこの間もありましたね。「#7119」ですね。ちょっと覚えておきます。
小高 はい。そして今日は、子どもの適切なかかり方について教えていただきます。
大前 これはちょっとしっかりと聞かせてください!
小高 前田さんにつボイさんと私、小高でうかがっております。
大前さん先週、このコーナーでは前田さんに救急外来について教えていただいたんですよ。で、救急車を呼ぶか、病院へ行くか迷うときってありますよね。そういうときは、まず救急あんしんセンター「#7119」にかけてくださいということなんです。電話先にはドクターや看護師さんがいらっしゃって、病院へ行けばいいのか、それとも救急車を呼ぶべきか教えてくれるんです。
大前 これ本当に、子どもが今1歳半で、これ思うことめっちゃあるんですよ。ほんとこの間もありましたね。「#7119」ですね。ちょっと覚えておきます。
小高 はい。そして今日は、子どもの適切なかかり方について教えていただきます。
大前 これはちょっとしっかりと聞かせてください!
小高 前田さんにつボイさんと私、小高でうかがっております。
前田 おそらく夕方とか夜、クリニックが閉まった後、お母さん方すごく心配されると思うんです。まず先週の放送で「#7119」のお話を聞いていただいたと思います。そこで、お母さまを含めた保護者さまのためのお助け道具があります。これも覚えていただきたいんですが、「#8000」という電話番号があります。これは小児救急電話相談といいまして、全国どこからでもかけていただけます。もちろんこれも無料なので、大人の「#7119」の子ども専用版というふうにお考えになってください。
小高 はい。
前田 やはりこれも夜間休日もすべて対応が可能ですし、電話には看護師さんが出てくれまして、その後ろに小児科の先生も控えてくれていますので、お子様の症状に関しての対処方法とか、すぐに受診が必要かどうかという判断もしてくれます。そういったものがまずはお助け道具としてあります。
小高 はい。
前田 あともう一つ、これは今スマートフォンを皆さん使われると思いますので、「子どもの救急」というウェブサイトがありますので、このサイトでお子さんの年齢とか症状を入れていただくと、質問に答えてくれて、すぐ受診とか、あるいはお家でこういう看護をしてくださいというような目安が表示されるというものもありますね。とはいえ、一番大事なのはお母さんの目利きなんです。いつもと何が違うのか、そういったところをしっかりと手がかりを集めていただいて、その情報を先程の「#8000」にお伝えいただいたり、もし病院にかかるということになっても、お医者様に伝えなければいけないので、それがやはり一番の診断材料になってきますね。
小高 子どものことなんだけど、電話するのはやっぱり親で、子どもの様子を説明しなきゃいけないんですが、どこをどう説明したらいいのかなっていうのは思いますよね。
前田 そうですよね。チェックポイントが大きく分けると4つあります。まず1つ目は「食べる、飲む」。
つボイ はい。
前田 例えばミルクや母乳をいつも通り飲めていたり、食欲というのに何か変わりがないかというのが1つ目ですね。2つ目は「寝る」。いつも通り眠れているのかとか、ぐずって眠れないのとか、ぐったりして寝てしまってるとか。そういったところをチェックしてください。
小高 はい。
前田 3番目。これは子どもなのでよく動くと思うんですが「遊ぶ」。遊ぶかどうか、機嫌はどうですか?活気はありますか?いつも通りのおもちゃに興味を示してますか?っていうところを見てください。そして、最後4番目は「出す」なんですけども、おしっこやうんちの回数ですとか、量とか色とか状態は何か変わりがありますか?こういうのをちょっとチェックしていただきたくて。ここでもスマートフォンがとても役に立つんです。
小高 はい。
前田 例えば先生であったり、電話で咳の様子を伝える時に、コンコンという咳なのか、ゼーゼーという咳なのかとか、表現って難しいじゃないですか。
つボイ 録音できるのか!
前田 おっしゃる通りです。録音や動画を見せれるとより良いでしょうね。そういった意味で言うと、先程の便の状態とかも画像で捉えてしまえると、こういう色なんだねとか、こういう状態なんだねっていうのは非常に伝わりやすいです。ですから、ちょっと恥ずかしいなと思われるかもしれませんが、お子様の正確な診断のためにとても有効な方法ですので、ぜひご活用いただきたいと思います。
小高 これね、普段そう言われたらそうなんだって思うんですが、子供の様子が相当大変な感じになってる時って、もう親が動揺しちゃって。こういう写真を撮るとか録音をするとか、もう頭がそこに全くいかないぐらいパニックになってることって多いと思うんですが。普段から電話の傍にメモかなんか貼っておくとかするといいのかもしれませんね。
つボイ 正常な時にこの放送で聞いたことを覚えておいていただいて、そういう時に思い出して写真を撮るとか、録音をするとかできるようにっていうことですよね。
前田 ちなみに先週の放送でこういった時はすぐ「119」ですという話をさせてもらったんですが、お子様にも本当に危険なサインはあります。例えば陥没呼吸と言うんですが、胸がペコペコ息をするたびに凹んでしまうような呼吸、こういった時は肩でもすごく息をしてると思うので、非常に呼吸が苦しそうな時。あとは意識障害が起こってる時ですね。呼びかけても反応しない、ぐったりしてしまっている時。後は痙攣ですね。お子様が痙攣すること自体はあるんですけども、その痙攣が5分以上続いてるような状態。こういった時はもう、非常に危険な状態に瀕し始めています。こういった場合はすぐに「119」におかけいただければと思います。
小高 はい。
前田 やはりこれも夜間休日もすべて対応が可能ですし、電話には看護師さんが出てくれまして、その後ろに小児科の先生も控えてくれていますので、お子様の症状に関しての対処方法とか、すぐに受診が必要かどうかという判断もしてくれます。そういったものがまずはお助け道具としてあります。
小高 はい。
前田 あともう一つ、これは今スマートフォンを皆さん使われると思いますので、「子どもの救急」というウェブサイトがありますので、このサイトでお子さんの年齢とか症状を入れていただくと、質問に答えてくれて、すぐ受診とか、あるいはお家でこういう看護をしてくださいというような目安が表示されるというものもありますね。とはいえ、一番大事なのはお母さんの目利きなんです。いつもと何が違うのか、そういったところをしっかりと手がかりを集めていただいて、その情報を先程の「#8000」にお伝えいただいたり、もし病院にかかるということになっても、お医者様に伝えなければいけないので、それがやはり一番の診断材料になってきますね。
小高 子どものことなんだけど、電話するのはやっぱり親で、子どもの様子を説明しなきゃいけないんですが、どこをどう説明したらいいのかなっていうのは思いますよね。
前田 そうですよね。チェックポイントが大きく分けると4つあります。まず1つ目は「食べる、飲む」。
つボイ はい。
前田 例えばミルクや母乳をいつも通り飲めていたり、食欲というのに何か変わりがないかというのが1つ目ですね。2つ目は「寝る」。いつも通り眠れているのかとか、ぐずって眠れないのとか、ぐったりして寝てしまってるとか。そういったところをチェックしてください。
小高 はい。
前田 3番目。これは子どもなのでよく動くと思うんですが「遊ぶ」。遊ぶかどうか、機嫌はどうですか?活気はありますか?いつも通りのおもちゃに興味を示してますか?っていうところを見てください。そして、最後4番目は「出す」なんですけども、おしっこやうんちの回数ですとか、量とか色とか状態は何か変わりがありますか?こういうのをちょっとチェックしていただきたくて。ここでもスマートフォンがとても役に立つんです。
小高 はい。
前田 例えば先生であったり、電話で咳の様子を伝える時に、コンコンという咳なのか、ゼーゼーという咳なのかとか、表現って難しいじゃないですか。
つボイ 録音できるのか!
前田 おっしゃる通りです。録音や動画を見せれるとより良いでしょうね。そういった意味で言うと、先程の便の状態とかも画像で捉えてしまえると、こういう色なんだねとか、こういう状態なんだねっていうのは非常に伝わりやすいです。ですから、ちょっと恥ずかしいなと思われるかもしれませんが、お子様の正確な診断のためにとても有効な方法ですので、ぜひご活用いただきたいと思います。
小高 これね、普段そう言われたらそうなんだって思うんですが、子供の様子が相当大変な感じになってる時って、もう親が動揺しちゃって。こういう写真を撮るとか録音をするとか、もう頭がそこに全くいかないぐらいパニックになってることって多いと思うんですが。普段から電話の傍にメモかなんか貼っておくとかするといいのかもしれませんね。
つボイ 正常な時にこの放送で聞いたことを覚えておいていただいて、そういう時に思い出して写真を撮るとか、録音をするとかできるようにっていうことですよね。
前田 ちなみに先週の放送でこういった時はすぐ「119」ですという話をさせてもらったんですが、お子様にも本当に危険なサインはあります。例えば陥没呼吸と言うんですが、胸がペコペコ息をするたびに凹んでしまうような呼吸、こういった時は肩でもすごく息をしてると思うので、非常に呼吸が苦しそうな時。あとは意識障害が起こってる時ですね。呼びかけても反応しない、ぐったりしてしまっている時。後は痙攣ですね。お子様が痙攣すること自体はあるんですけども、その痙攣が5分以上続いてるような状態。こういった時はもう、非常に危険な状態に瀕し始めています。こういった場合はすぐに「119」におかけいただければと思います。
大前 なるほどね。だから大人が「#7119」で、子供はシャープ「#8000」。家も先月ぐらいかな。初めて子供が熱出したと思ったら、子供って本当にガガガガガって39度ぐらいまで熱が上がって。
小高 そうそう。しかもちっちゃい子だと自分でどのくらいまでしんどいかってなかなか説明できないから。
大前 僕は本当に初めてのことで、もうわかんないからすぐにスマホを取って、それこそ救急車呼ぼうとしたんですけど。すぐに奥さんが違う違うちゃんと順番があんねん!って、多分その時に奥さんかけてたんちゃうかな。それで先生が痙攣すると本当に危ないから、とにかくしっかり見といてあげてくださいって。とにかく不安だったんで、こういう時にどうすればいいのかすぐ教えてもらえる場所があると安心しますね。
小高 ね。それだけで随分安心だと思いますんで、覚えておきましょう。来週も前田さんに病院の上手な使い方を教えていただきます。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
大前 はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~病院の上手な使い方~」でした。
小高 そうそう。しかもちっちゃい子だと自分でどのくらいまでしんどいかってなかなか説明できないから。
大前 僕は本当に初めてのことで、もうわかんないからすぐにスマホを取って、それこそ救急車呼ぼうとしたんですけど。すぐに奥さんが違う違うちゃんと順番があんねん!って、多分その時に奥さんかけてたんちゃうかな。それで先生が痙攣すると本当に危ないから、とにかくしっかり見といてあげてくださいって。とにかく不安だったんで、こういう時にどうすればいいのかすぐ教えてもらえる場所があると安心しますね。
小高 ね。それだけで随分安心だと思いますんで、覚えておきましょう。来週も前田さんに病院の上手な使い方を教えていただきます。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
大前 はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~病院の上手な使い方~」でした。