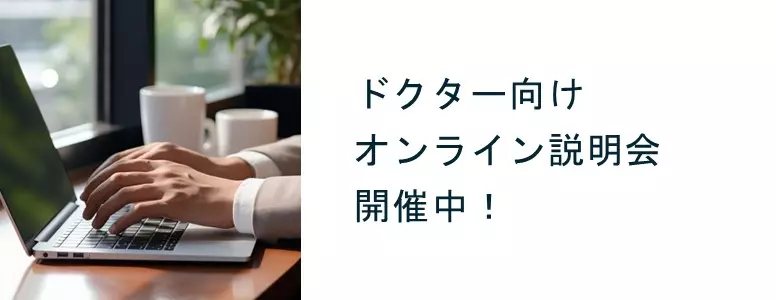第13回 ロボット支援手術~ロボット支援手術のいま

小高 水曜日のこの時間は「健康のつボ!~ロボット支援手術について」、一宮西病院 外科副部長で消化器低侵襲手術センター副センター長の岡田 和幸先生に教えていただいてきました。今日がこのシリーズの最終回となります。
つボイ 私はまだロボット支援手術の経験はないんですが、もし何かの手術が必要となったときは、低侵襲という言葉にやっぱり惹かれますね~。
小高 最終回の今日は「ロボット支援手術」とはどんなものなのか、そのメリットについて改めて岡田先生に教えていただきます。
つボイ 私はまだロボット支援手術の経験はないんですが、もし何かの手術が必要となったときは、低侵襲という言葉にやっぱり惹かれますね~。
小高 最終回の今日は「ロボット支援手術」とはどんなものなのか、そのメリットについて改めて岡田先生に教えていただきます。
岡田 従来の手術というのは、最初は開腹手術がメインでした。そこから1980年代に小さい孔を何カ所か開け、カメラを使った腹腔鏡手術が行われるようになってきました。低侵襲でクオリティも高かったのですが、やはりその孔から鉗子という長い棒を入れて、その先がパカパカ開くような動きしかできなかったので、開腹手術と比べて手術をする難しさがありました。特にお腹の奥の方、深い所の手術になってくると動きの幅が大きくなったり、手ぶれが起きやすくなったりして難しい。それを補うものとしてロボット支援手術が開発されてきました。
つボイ はい。
岡田 そして、日本でも2010年前後からいろいろな手術で許可されるようになってきました。なので、いわばロボット支援手術というのは腹腔鏡下手術の進化形と言えるかなと思います。
小高 ロボットはアーム、手が4本でしたよね。
岡田 そうですね。ロボットには手が4本ありまして、1つがカメラで他の3つが組織をつまんだり切ったり縫ったりするような様々な用途の鉗子類が付いています。先程鉗子の先がパカパカ開くだけなのが腹腔鏡手術とお話ししましたけど、それに比べてロボット支援手術では、鉗子に関節がついてます。関節があることでまるで人の手のような動きをすることができて、あたかも自分の小さな手がお腹の中に入って手術をしているような感覚で細かい作業ができます。
小高 人間の大きな手よりも、もっと小さい手で細かい作業ができると。
岡田 ロボットの孔というのは8ミリあるいは6ミリ程で、そこから入る鉗子なので、人間の手と比べるとかなり小さいものが入って作業ができるということです。カメラも3Dハイビジョンで、立体の綺麗な映像で見ることができますし、コンピューター制御で、手ぶれが補正されるところもやはり大きいところです。
つボイ 精密にピンポイントでできるんでしょうね。
小高 人間だから細かいところやればやろうとするほどちょっと震えちゃったりね。
岡田 やっぱり多少震えますが、それがだいぶ補正されます。
小高 そういったロボットによって非常に正確な手術というのが可能になったということですね。
岡田 そういった優れた機能で、癌をしっかり治すという根治性と、機能の温存、残すべきところはしっかり残すというところの両立が可能になってきてるのかなと思います。
小高 やっぱり開腹手術だと、ガバっと切ってガバッと開けますから、それを縫い合わせた後、塞がるまで随分時間がかかって入院期間も長くなるそうですね。小さい孔で済むということですから、患者さんにとっても非常に楽ですよね。
岡田 低侵襲というのも患者さんにとって優しいと思います。出血量も少なくなりますし、痛みはもちろん少ないですし、退院までの期間も短くなると言われています。
つボイ 聞いてると何か心強い気持ちになりましたね。
小高 まだまだね、いろんな課題なんかもあるんでしょうけど、今後の進化なんかも期待もできそうですね。どんどんいろんな人がこのロボット支援手術によって、楽に、簡単に大きな病気が治るというふうになっていってくれるといいですよね。
岡田 まだまだ2010年ぐらいからなので、始まったばかりですし、これからどんどん改良していかないといけない部分もあると思います。ロボット支援手術というのは、楽にしっかり治すということに対して、非常に良い手段だと考えています。
つボイ はい。
岡田 そして、日本でも2010年前後からいろいろな手術で許可されるようになってきました。なので、いわばロボット支援手術というのは腹腔鏡下手術の進化形と言えるかなと思います。
小高 ロボットはアーム、手が4本でしたよね。
岡田 そうですね。ロボットには手が4本ありまして、1つがカメラで他の3つが組織をつまんだり切ったり縫ったりするような様々な用途の鉗子類が付いています。先程鉗子の先がパカパカ開くだけなのが腹腔鏡手術とお話ししましたけど、それに比べてロボット支援手術では、鉗子に関節がついてます。関節があることでまるで人の手のような動きをすることができて、あたかも自分の小さな手がお腹の中に入って手術をしているような感覚で細かい作業ができます。
小高 人間の大きな手よりも、もっと小さい手で細かい作業ができると。
岡田 ロボットの孔というのは8ミリあるいは6ミリ程で、そこから入る鉗子なので、人間の手と比べるとかなり小さいものが入って作業ができるということです。カメラも3Dハイビジョンで、立体の綺麗な映像で見ることができますし、コンピューター制御で、手ぶれが補正されるところもやはり大きいところです。
つボイ 精密にピンポイントでできるんでしょうね。
小高 人間だから細かいところやればやろうとするほどちょっと震えちゃったりね。
岡田 やっぱり多少震えますが、それがだいぶ補正されます。
小高 そういったロボットによって非常に正確な手術というのが可能になったということですね。
岡田 そういった優れた機能で、癌をしっかり治すという根治性と、機能の温存、残すべきところはしっかり残すというところの両立が可能になってきてるのかなと思います。
小高 やっぱり開腹手術だと、ガバっと切ってガバッと開けますから、それを縫い合わせた後、塞がるまで随分時間がかかって入院期間も長くなるそうですね。小さい孔で済むということですから、患者さんにとっても非常に楽ですよね。
岡田 低侵襲というのも患者さんにとって優しいと思います。出血量も少なくなりますし、痛みはもちろん少ないですし、退院までの期間も短くなると言われています。
つボイ 聞いてると何か心強い気持ちになりましたね。
小高 まだまだね、いろんな課題なんかもあるんでしょうけど、今後の進化なんかも期待もできそうですね。どんどんいろんな人がこのロボット支援手術によって、楽に、簡単に大きな病気が治るというふうになっていってくれるといいですよね。
岡田 まだまだ2010年ぐらいからなので、始まったばかりですし、これからどんどん改良していかないといけない部分もあると思います。ロボット支援手術というのは、楽にしっかり治すということに対して、非常に良い手段だと考えています。
つボイ ロボット支援手術のこのロボットは、これからもどんどん何か進化していくような感じですね。
小高 そうですね。そして今以上にいろいろな手術に使われていくことになるんでしょうね。
つボイ 何よりも低侵襲であることは、患者さんにとっては負担が少ないということですから、ありがたいことだなと思っております。
小高 はい。一宮西病院の岡田先生でした。ありがとうございました。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
つボイ はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~ロボット支援手術~」でした。
小高 そうですね。そして今以上にいろいろな手術に使われていくことになるんでしょうね。
つボイ 何よりも低侵襲であることは、患者さんにとっては負担が少ないということですから、ありがたいことだなと思っております。
小高 はい。一宮西病院の岡田先生でした。ありがとうございました。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
つボイ はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~ロボット支援手術~」でした。