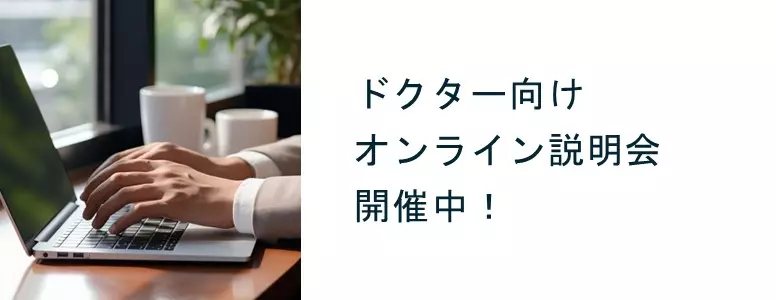院内感染対策に関する取組事項
院内感染対策に関する基本的な考え方
- 一宮西病院(病院)は、患者さまが健康になるための医療サービスを提供している。にもかかわらず、患者さまが院内で入院時とは別の感染症に罹り、不利益を被ることはあってはならないことである。そこで病院はこのような医療関連感染を防ぐために、組織的に取り組んでいる。
- 万が一院内感染が発生した時には、可及的速やかに原因を究明し、院内感染を制圧・終息させるとともに、再発防止策の立案、感染防止対策を徹底する。
- 職員に対しては、感染防御に関する知識と技術の向上および職業感染防止に努める。
- 病院は、その理念である「街と人が明るく健康でいられますように」を基に本指針を定め、あらたな感染症にも迅速的に対応できるよう組織的に継続的に院内感染対策に取り組む所存である。
院内感染対策のための組織に関する事項
Ⅰ. 院内感染対策を推進するため、本指針に基づき、以下の委員会等を設置する。
Ⅱ. ICC、ICT、AST、感染対策室は病院長直轄の組織であり、病院長から指示命令を受け活動する。
- 感染対策委員会(ICC)
院内感染対策についての最高決議機関としての役割を担い、決議内容は院長の承認を受け、全職員に周知される。原則月1回の定例開催とする。 - 院内感染対策実行チーム(ICT)
院内感染防止のための調査分析と対策を行う為、週1回以上のラウンドを組織横断的に遂行、週1回ICTで審議する。またその内容をICCへ報告する。 - 抗菌薬適正使用支援チーム(AST)
抗菌薬の適正使用を支援し、AMRアクションプラン(適切な抗菌薬を必要な場合に限り適切な量と期間を使用する)を実践し、その内容をICCへ報告する。 - 感染対策室
病院感染に関する問題を迅速に解決できるよう窓口になるとともに、医療関連感染からすべての患者・職員を守るため、職員教育を含め1~3と連携して日々感染防止に携わる業務を行う。
Ⅱ. ICC、ICT、AST、感染対策室は病院長直轄の組織であり、病院長から指示命令を受け活動する。
院内感染対策のための職員研修に関する事項
- ICTやASTは、全職員や専門職種(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)を対象に院内感染対策全般や抗菌薬の適正使用に関する研修会を年2回以上開催する。
- 研修は、院内感染対策の基本的な考え方等や抗菌薬についての適正な使用に関する考え方を全職員や該当する専門職員に周知徹底することを通じて、職員個々の感染対策への意識向上を図り、病院全体の院内感染対策を向上させることを目的とする。
- 研修が実施される際には、職員は受講するように努めなければならない。
感染症の発生状況の報告に関する基本方針
- 法律の定めるところにより、感染症患者等を診断した場合は保健所へ届出を行う。
- ICT及びASTは、サーベイランス(病原微生物別の院内感染症患者数、各種細菌の検出状況、抗菌薬の使用状況等)を週1回作成し、ICCで情報提供する。
院内感染発生時の対応に関する基本方針
- 職員は、院内感染発生が疑われる時やアウトブレイクが発生した時には、直ちにICT・感染対策室に報告する。
- ICT・感染対策室は迅速に状況確認・調査及び感染対策を行い、感染拡大防止に努める。また委員長は必要に応じて、ICCを臨時開催する。
その他
- ICTは、院内感染対策のためのマニュアルを整備し、適宜改訂を行う。
- 本指針の内容を含め、患者及びその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じるものとする。
- 当院は、感染対策向上加算1の届出施設です。
- 当院は、年4回以上連携施設とのカンファレンスを行っています。
<感染対策向上加算>連携施設
| 加算1連携 |
|
| 加算2連携 |
|
| 加算3連携 |
|
<外来感染対策向上加算>
|