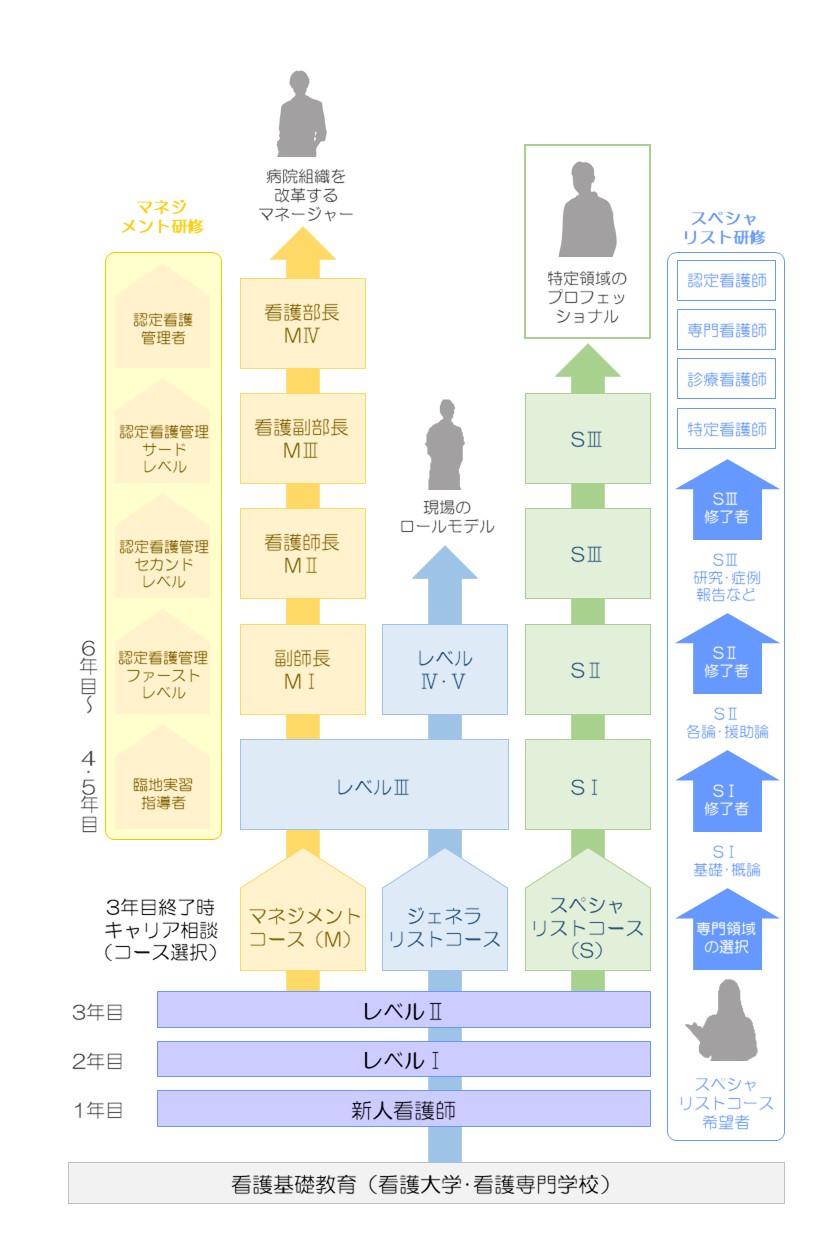認定看護師取得へのプログラム

より患者さんのために寄り添って看護ができるなら、
今よりもっと頑張りたい、もっと役に立ちたい、
もっとスキルを身につけたい。
そして、ずっとこの仕事を続けたい。
患者さんが笑顔になるのを見たいから。
上を目指して、
今以上の看護をするために自分も成長する。
自分自身に力をつけて
自分らしく患者さんと接して。
自分にしかできない看護が、
もっと、きっと、あるはず。
認定看護師とは

認定看護師の役割

認定看護師は特定の看護分野において、以下の3つの役割を果たします。
- 【実践】
個人、家族及び集団に対して、高い臨床推論力と病態判断力に基づき、熟練した看護技術及び知識を用いて水準の高い看護を実践する。 - 【指導】
看護実践を通して看護職に対し指導をおこなう。 - 【相談】
看護職等に対しコンサルテーションをおこなう。
認定看護師の声
認定看護師01
北澤 美砂 [ 皮膚・排泄ケア ]

PROFILE プロフィール
臨床看護経験の大半はICU。看護の力で患者さんの皮膚症状が改善した経験を契機に、皮膚・排泄ケアの学習をさらに深めたいと思い、認定看護師を目指す。難治性の創傷ケア等は難しい症例だからこそ自分の出番。できないと諦めたくない、できる方法を考えたい。看護の可能性を信じて自己研鑽に励む毎日。
まだまだある。
看護を深めて、患者さんを支えたい。
ICUでのケアで、強い思いに。
私が認定看護師を目指すようになったのは、看護師になって5~6年目のころ。きっかけはICUで経験した、陰部の皮膚が荒れてただれた患者さんのケアでした。ケア中はとても辛そうで、この患者さんのために何かできないかと看護師同士で話し合い、スキンケアの方法を工夫しながら取り組みました。その結果、看護の力で患者さんの辛そうな表情や反応、皮膚症状が改善したのを目の当たりにし、看護することの喜びを実感できたのです。皮膚・排泄ケアの看護は全年齢が対象で、治療だけでなく予防のためにも取り組むべき看護。その看護を深めて、患者さんや患者さんを支える人の力になりたいと思うようになったのです。
認定看護師の教育課程を受講するまでは、仕事をしながら受験勉強や症例の振り返りなどを進めていましたが、引っ越しや仕事の引継ぎもあったので時間的な余裕がなく焦ることも。教育課程は集中して学べる環境でしたが、座学や模型を用いた学習が多く患者さんと接する機会が少ない分、自分の抱く看護観と向き合うことができたと思います。習得することが多く心が折れそうになることもあったのですが、仲間と共に専門分野について学べることが楽しいと思えたので大変なことも乗り越えられました。

どのような状況でも看護を諦めず、患者さんと支える人の要望に応えたい。
私はケアを提供するだけではなく、患者さんの思いをじっくりと聞いて意思決定を支援したり、スタッフと治療や看護の目標を共有したりして、患者さんの力になれるよう活動しています。スタッフを指導するときは、指導したことが適切にケアに活かせるよう、相手のスキルに合わせておこなうようにしています。また、院内の褥瘡対策委員会に参加し、褥瘡回診や院内研修などの活動に携わり、褥瘡予防や発生後の早期治癒に努めていきたいです。
患者さんと支える人たちの「困った」「つらい」「なんとかしたい」に応えられるよう、皮膚・排泄ケア分野の学会への参加や学会発表、看護研究に取り組み、日々自己研鑽に励んでいます。




皮膚・排泄ケア看護の喜びをスタッフにも伝えたい。
皮膚・排泄ケア領域には、看護の力でできることがたくさんあります。しかし、私一人の力だけではケアの実践や継続は不可能です。私が持つ知識や技術を活用してもらえるよう、看護実践だけでなく指導をおこないながら、スタッフの皆さんと共に看護の質の向上を目指していきたいです。
一方で、患者さんの目線から考えると病院は一つの通過点であり、生活の基盤は地域にあります。皮膚・排泄ケアの看護を院内だけでなく地域にも広がるよう活動の場を拡大し、地域で暮らす患者さんの力になれることが今の目標。私の活動を通して皮膚・排泄ケアに興味を持ってくれたり、認定看護師として一緒に活動したいと思ってくれたりする仲間が増えるとうれしいです。
1日の流れ
-
8:30-始業
褥瘡保有患者さまや褥瘡ハイリスク患者さまの情報収集をおこなう。
-
9:30-病棟ラウンド / 相談対応
褥瘡ケアを中心に、創傷やストーマ、排泄ケアの相談に応じて病棟・外来でケアをおこなう。
-
11:30-看護記録
-
12:00-休憩
-
13:00-病棟ラウンド / 相談対応
-
14:00-褥瘡ハイリスク患者カンファレンス(週1回) / 褥瘡回診(週1〜2回)
-
15:00-看護記録 / 褥瘡に関するデータ集計
-
16:00-委員会など
認定看護師02
堀 知恵 [ 集中ケア ]

PROFILE プロフィール
集中ケア認定看護師の課程を東京の教育機関で履修。休職して東京に住みながらの毎日だった。教育機関への合格を目指した受験期を含め、人生で一番勉強したと振り返る。現在は後輩のロールモデルの一つであることを意識して、仕事と勉強を両立した日々を過ごす。
自信を持って意見を言える。
医師のように専門領域はないのか。
その疑問が目指すきっかけに。
当時入職1年目、手術室に配属されました。そこで疑問に思ったことが、認定看護師を目指すきっかけになりました。各診療科の医師が手術を担当するのに、看護師に専門家はいないのだろうか。そこで調べた際に、認定看護師の存在を知ったのです。私自身、専門性を持ちたいという希望があり、その気持ちにマッチした制度に心が躍ったことを覚えています。
その後、救命センターへ異動。患者さんの情報を収集し、情報を整理・分析・評価するアセスメントがとても素晴らしい認定看護師がいました。当初は「手術看護」での認定を考えていましたが、この出会いによって「集中ケア」での認定看護師を目指したいと心が決まりました。
ただ、取得したいといっても、簡単なものではありません。その分野での経験も、認定看護師教育機関での6ヶ月間の教育課程の履修も必要です。なかなかタイミングが合わずにいたのですが、後押ししてくれたのは病院のサポート体制でした。教育機関に通うと約半年間、仕事ができません。私の場合は教育機関が東京にあったため住居も必要で、一宮西病院からその間も基本給と住宅手当を支給していただけたことで、退職することなく続けることができました。

自己研鑽に励み、専門知識を後輩へ伝える。
院外活動にも積極的に参加しており、看護系雑誌や参考書の執筆、学会ではセッションの座長を務めるなど、より専門性を磨くため努力を続けています。自身を高める一方で、後輩指導にも力を入れています。後輩の知識が増え、自信を持つことでより良い看護ができるようになれば、その経験に喜びを感じ、さらにその後輩を指導したいと思えます。一宮西病院において、その好循環を生み出すための役割も担っていると考えています。それは後輩のためでもあり、患者さんのためでもあると私は思います。やはり患者さんが回復された姿を見るのが何よりも幸せです。


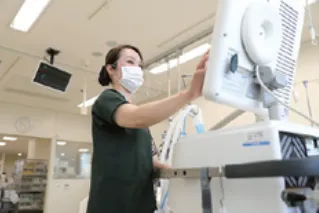

患者さんと向き合い信頼してもらえる存在に。
患者さんやご家族さんから「堀さんに相談したい」、「堀さんに何か聞けば大丈夫」と思っていただける存在になりたいです。私がそうだったように、私の姿を後輩が見ることで、その後輩が自分も勉強して認定看護師になりたいと思ってくれたらとてもうれしいですね。
これから『街と人が明るく健康でいられますように』という病院の理念のもと、院内にとどまらず地域へと活動の場を広げ、活躍できればいいなと思います。また、院外活動を通して、より多くの看護師たちに、認定看護師になることを一つの道として考えてほしいと思っています。そのためにもまずは、一人ひとりの患者さんに真剣に向き合い、すべての知識を活かして、できるだけのことをしたいと思います。
1日の流れ
-
8:00-出勤
ICU入室中の患者さまの情報収集をおこなう。
-
8:30-朝礼
その日の入退室患者さまの把握、夜勤リーダーから全体の申し送り
-
8:45-回診
麻酔科医師のICU入室患者回診に同行し、情報共有等します。
-
9:00-カンファレンス
患者カンファレンスやインシデントに対して、リスクカンファレンスをおこなう。
-
10:00-認定活動 ※ICUの状況に応じて、清潔ケア等の業務をおこなう / 呼吸ケアチーム(RST)が介入している患者データの収集 / 勉強会やカンファレンス等の資料作り・準備
-
13:30-休憩
-
14:30-情報収集
呼吸ケアチーム(RST)でラウンドする患者さまの情報収集をおこなう。
-
15:00-呼吸ケアチーム(RST)回診
-
16:00-日報作成
その日の活動内容をまとめ、所属長・認定師会委員長・看護部長に報告します。
-
16:30-病棟カンファレンス
一般病棟で急変した患者さまについて相談を受けたときは、振り返りやデスカンファレンスに参加します。カンファレンスでは、急変のターニングポイントや改善点、知識の補填等の指導をおこないます。
-
17:20業務終了
認定看護師03
小森 彩 [ 摂食嚥下障害 ]

PROFILE プロフィール
家庭では2児の母として家事や育児に奮闘し、仕事では認定看護師として患者さんと向き合いながら、NST委員会の活動や、後輩指導も行う。知識が増えたことでこれまで見えてこなかった新たな課題にも挑戦する日々。その中で、共に働く仲間との知識共有に力を入れることで患者さんのために貢献しようという努力は怠らない。
成長をあきらめない。
毎日のように増えていく知識が、
必ず患者さんのためになると思えた。
「摂食嚥下障害看護」に興味を持ったのは看護師として1年目のこと。当時は脳神経外科・耳鼻科・口腔外科の看護師をしていたのですが、脳梗塞やがんなどの理由で、食べることが難しくなる患者さんは少なくありませんでした。何とか口から食べ続けたいと望む患者さんの思いに寄り添い、「こうすれば食べられるのではないか」と具体的な提案をしていたのが「摂食嚥下障害看護」の認定看護師でした。その姿に憧れをもちました。しかし、産休育休や子育てと仕事の両立もあり、なかなか挑戦する勇気がもてませんでした。
ただ、看護師として経験を重ねるなかで、自身がしている看護に自信が持てない場面や、説得力が足りないと思う場面があると感じそれを上司に相談したところ、「悩んでいるなら一度受験してみては、応援するよ」と背中を押していただきました。上司や同僚、そして何より家族が応援してくれたことで受験を決断できました。また、受験費用や入学費用について、病院から経済的な面でのサポートがあったことも決断できた理由の一つです。変わらず子育てと並行しての勉強だったため、時間をつくる苦労はありました。しかし、知識が増えることを毎日のように実感でき、「必ず患者さんのためになる」という実感がモチベーションになっていました。
認定看護師になっても悩みは多い。それを乗り越える努力を続けている。
また、今後は日々の看護のなかで出てくる「摂食嚥下」についての「相談」をスタッフから受ける機会も増えてくると思います。患者さんによりよい看護が提供できるように、私一人だけではなく、患者さんのために悩む現場の看護師と共に考えていけたらと思っています。患者さんの思いに寄り添い、みんなでその回復を支援していきたいです。
看護師となっても、まだまだ悩むことは多いです。勉強したことで様々な考え方を得られたからこそ、一つの判断をする際にとても慎重になったと感じます。食べることだけでなく、昨日より今日、何か一つでも良くなっている。患者さんにそうなってもらえるよう、私自身これからも努力をつづけていきます。




仕事と家庭の両立、見本となれるように。
院内には多様な領域の認定看護師がおり、それぞれから講義や指導を受けられる機会があります。新人看護師だけでなく、一定の経験を積んだ看護師も対象であり、私も勉強する側の一人として自己の専門分野の知識だけでなく、オールマイティに知識を増やしたいと思っています。
欲張りかもしれませんが仕事と家庭を両立しながら、それでも看護師として成長していきたい。産休育休などでキャリアが中断することはあるかもしれませんが、子どもがいてもスキルアップに熱を持って取り組む仲間が増えていったらうれしいです。一宮西病院にはその思いを支援する制度があります。チャレンジする後輩たちの参考になれるよう、頑張っていきます。
1日の流れ
-
8:30-病棟業務など
病棟業務を兼ねて、摂食嚥下障害患者さまへのケアや回診患者さまの情報収集をおこなう。
-
12:30-休憩
-
13:30-病棟カンファレンス
-
14:00-栄養サポートチーム(NST)回診
F6〜F2病棟
-
16:00-F9病棟嚥下カンファレンス
-
16:30-嚥下カンファレンス
-
17:00-病棟業務
認定看護師取得サポート
認定看護師取得までのサポート
| 内容 | 金額の例 Aさんの場合 約81%のサポート |
金額の例 Bさんの場合 約79%のサポート |
|
| 病 院 か ら の 費 用 援 助 |
入学試験受験料【不合格まで2回支給】 | ¥50,000 | ¥50,000 |
| 入学試験受験時の交通費・宿泊費(県内外)【不合格まで2回支給】 | ¥30,000 | ¥50,000 | |
| 入学金 | ¥50,000 | ¥50,000 | |
| 授業料 | ¥700,000 | ¥1,000,000 | |
| 認定審査申請料 | ¥51,700 | ¥51,700 | |
| 認定審査に係る交通費 | ¥800 | ¥1,000 | |
| 認定看護師登録料 | ¥51,700 | ¥51,700 | |
| 通勤手当【教育機関へ通学可能な場合】 | 実費・病院負担 | 実費・病院負担 | |
| 住宅手当(上限5万円/月)【教育機関が県外の場合】 | ¥300,000 | ¥500,000 | |
| 帰省費(上限: 月1回・実費)【教育機関が遠方の場合、新幹線】 | ¥23,000 | ¥35,000 | |
| 更新料など | ¥38,000 | ¥38,000 | |
| 自 己 負 担 |
教材費 | ¥300,000 | ¥500,000 |
| 認定看護師取得にかかった実際の費用 | ¥1,595,200 | ¥2,327,400 | |
| →うち病院からのサポート費用合計 | ¥1,295,200 | ¥1,827,400 | |
| 自己負担額合計 | ¥300,000 | ¥500,000 | |
認定看護師取得後のサポート(資格手当)
| 内容 | 金額 |
| 専任の認定看護師の場合 | ¥10,000/月 |
| 専従の認定看護師の場合 | ¥20,000/月 |
A課程 認定看護師 21分野
| 認定看護師分野名 | 知識と技術(一部) |
| 救急看護 |
|
| 皮膚・排泄ケア |
|
| 集中ケア |
|
| 緩和ケア |
|
| がん化学療法看護 |
|
| がん性疼痛看護 |
|
| 訪問看護 |
|
| 感染管理 |
|
| 糖尿病看護 |
|
| 不妊症看護 |
|
| 新生児集中ケア |
|
| 透析看護 |
|
| 手術看護 |
|
| 乳がん看護 |
|
| 摂食・嚥下障害看護 |
|
| 小児救急看護 |
|
| 認知症看護 |
|
| 脳卒中リハビリテーション看護 |
|
| がん放射線療法看護 |
|
| 慢性呼吸器疾患看護 |
|
| 慢性心不全看護 |
|
B課程 特定認定看護師 19分野
| 認定看護師分野名 | 知識と技術(一部) | 関連特定行為 |
| 感染管理 | 医療関連感染の予防・管理システムの構築 | |
| 医療管理感染の予防・管理に関する科学的根拠の評価とケア改善 | ||
| 医療関連感染サーベイランスの立案・実施・評価 | ||
| 身体的所見から病態を判断し、感染兆候がある者に対する薬剤の臨時投与ができる知識・技術 | 感染に係る薬剤投与関連 | |
| がん放射線療法看護 | 放射線治療を受ける対象の身体的・心理的・社会的アセスメント | |
| 再現性確保のための支援 | ||
| 急性期及び晩期有害事象に対する症状マネジメントとセルフケア支援 | ||
| 医療被曝を最小限にするための放射線防護策、安全管理技術 | ||
| がん薬物療法看護 | がん薬物療法の適正な投与管理とリスクマネジメント、暴露対策 | |
| がん薬物療法に伴う症状緩和 | ||
| 自宅での治療管理や有害事象に対応するための個別的な患者教育 | ||
| 患者・家族の意思決定支援と療養生活支援 | ||
| 緩和ケア | 痛みやその他の身体的・心理社会的・スピリチュアルな問題のアセスメント | |
| 全人的問題を緩和し、QOLを向上するための症状マネジメント | ||
| ・家族の喪失や悲嘆への対応 | ||
| クリティカルケア | 急性かつ重篤な患者の重篤化回避と合併症予防に向けた全身管理 | |
| ・安全・安楽に配慮した早期回復支援 | ||
| 身体所見から病態を判断し、侵襲的陽圧換気・非侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 | 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | |
| 身体所見から病態を判断し、持続点滴中の薬剤(カテコラミン、ナトリウム、カリウム又はクロール、降圧剤、糖質輸液又は電解質輸液、利尿剤)の投与量の調整を安全・確実にできる知識・技術 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | |
| 呼吸器疾患看護 | 呼吸症状のモニタリングと評価、重症化予防 | |
| 療養生活行動支援及び地域へつなぐための生活調整 | ||
| 症状緩和のためのマネジメント | ||
| 身体所見を病態判断し、侵襲的陽圧換気・非侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 | 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | |
| 在宅ケア | 生活の場におけるQOLの維持・向上とセルフケア支援 | |
| 対象を取り巻くケアシステムの課題に対する解決策の提案 | ||
| 生活に焦点をあてた在宅療養移行支援及び多職種との調整・協働 | ||
| 意思決定支援とQOLを高めるエンド・オブ・ライフケア | ||
| 身体所見から病態を判断し、気管カニューレの交換が安全にできる知識・技術 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | |
| 身体所見から病態を判断し、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換が安全にできる知識・技術 | ろう孔管理関連 | |
| 身体所見から病態を判断し、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去が安全にできる知識・技術 | 創傷管理関連 | |
| 手術看護 | 手術侵襲及びそれによって引き起こされる苦痛を最小限に留めるためのケア | |
| 手術中の患者の急変及び緊急事態への迅速な対応 | ||
| 患者及び家族の権利擁護と意思決定支援 | ||
| 身体所見から病態を判断し、経口用気管チューブ又は 経鼻用気管チューブの位置の調整ができる知識・技術 |
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 | |
| 身体所見から病態を判断し、侵襲的陽圧換気の設定の変更、人工呼吸器からの離脱ができる知識・技術 | 呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 | |
| 身体所見から病態を判断し、直接動脈穿刺法による採血、橈骨動脈ラインの確保ができる知識・技術 | 動脈血液ガス分析関連 | |
| 身体所見から病態を判断し、硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与及び投与量の調整ができる知識・技術 | 術後疼痛管理関連 | |
| 身体所見から病態を判断し、持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整ができる知識・技術 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 | |
| 小児プライマリケア | 重篤な状態にある児もしくは医療的ケア児に対する重症化予防 | |
| 外来及び地域等のプライマリケアの場におけるトリアージ | ||
| 家族の家庭看護力・育児力向上に向けたホームケア指導 | ||
| 不適切な養育または虐待の予防、早期発見と、子どもの事故防止 | ||
| 身体所見及び気管カニューレの状態を病態判断し、 気管カニューレの交換が行える知識・技術 |
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | |
| 新生児集中ケア | ハイリスク新生児の急性期の全身管理 | |
| 障害なき成育のための個別ケア | ||
| ハイリスク新生児と親への家族形成支援 | ||
| 不適切な養育または虐待のハイリスク状態の予測と予防 | ||
| 身体所見及び気管カニューレの状態を病態判断し、気管カニューレの交換が行える知識・技術 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 | |
| 心不全看護 | 心不全症状のモニタリングと評価、重症化予防 | |
| 療養生活行動支援及び地域へつなぐための生活調整 | ||
| 症状緩和のためのマネジメント | ||
| 身体所見から病態を判断し、持続点滴中の薬剤(カテコラミン、ナトリウム、カリウム又はクロール、降圧剤、糖質輸液又は電解質輸液、利尿剤)の投与量の調整を安全・確実にできる知識・技術 | 循環動態に係る薬剤投与関連 | |
| 腎不全看護 | 疾病の進展予防、合併症の早期発見と症状マネジメント、セルフケア支援 | |
| 腎代替療法の選択・変更・中止にかかわる自己決定に向けた支援 | ||
| 透析療法における至適透析の実現に向けた支援 | ||
| 急性血液浄化療法における血液透析器又は血液透析濾過器の操作及び管理を安全・確実にできる知識・技術 | 透析管理関連 | |
| 生殖看護 | 性と生殖の機能、その障害とリスク因子に関する知識に基づく妊孕性の評価 | |
| 性と生殖の健康課題に対する、多様な選択における意思決定支援 | ||
| 患者・家族の検査期・治療期・終結期の安全・安楽・納得を守る看護実践とケア調整 | ||
| 妊孕性温存及び受胎調節に関する指導 | ||
| 摂食嚥下障害看護 | 摂食嚥下機能とその障害の評価 | |
| 摂食嚥下機能の評価結果に基づく適切な援助・訓練方法の選択 | ||
| 誤嚥性肺炎、窒息、栄養低下、脱水の増悪防止に向けたリスク管理 | ||
| 糖尿病看護 | 血糖パターンマネジメント | |
| 病期に応じた透析予防、療養生活支援 | ||
| 予防的フットケア | ||
| 身体所見から病態を判断し、インスリンの投与量の調整ができる知識・技術 | 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 | |
| 乳がん看護 | 術後合併症予防及び緩和のための周手術期ケアと意思決定支援 | |
| ライフサイクルの課題を踏まえた、治療に伴う女性性と家族支援 | ||
| 乳房自己検診、リンパ浮腫等の乳がん治療関連合併症の予防・管理 | ||
| 身体所見から病態を判断し、創部ドレーンの抜去ができる知識・技術 | 創部ドレーン管理関連 | |
| 認知症看護 | 認知症の症状マネジメント及び生活・療養・環境の調整 | |
| 認知症の病期に応じたコミュニケーション手段の提案と意思決定支援 | ||
| 家族への心理的・社会的支援 | ||
| 身体所見から病態を判断し、抗けいれん剤、抗精神病薬及び抗不安薬の臨時の投与ができる知識・技術 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | |
| 脳卒中看護 | 重篤化回避のためのモニタリングとケア | |
| 早期離床と生活の再構築に向けた支援 | ||
| 在宅での生活を視野に入れたケアマネジメントと意思決定支援 | ||
| 身体所見から病態を判断し、抗けいれん剤、抗精神病薬及び抗不安薬の臨時の投与ができる知識・技術 | 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 | |
| 皮膚・排泄ケア | 褥瘡のトータルマネジメント | |
| 管理困難なストーマや皮膚障害を伴うストーマケア | ||
| 専門的な排泄管理とスキンケア | ||
| 脆弱皮膚を有する個人・リスクがある個人の専門的なスキンケア | ||
| 地域包括ケアシステムを視野に入れた同行訪問実施とマネジメント | ||
| 身体所見から病態を判断し、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去及び創傷に対する陰圧閉鎖療法ができる知識・技術 | 創傷管理関連 |