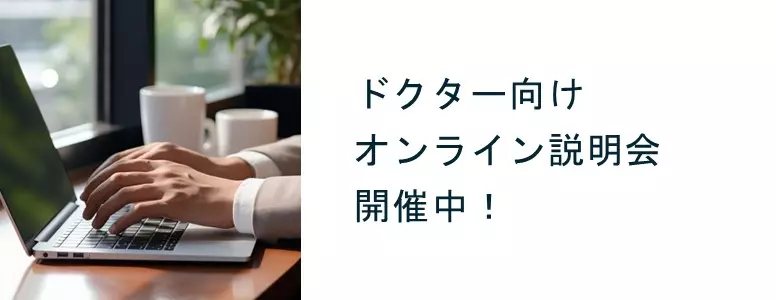第12回 ロボット支援手術~ロボット支援手術のこれから

小高 水曜日のこの時間は「健康のつボ!~ロボット支援手術について」、一宮西病院 外科副部長で消化器低侵襲手術センター副センター長の岡田 和幸先生に教えていただいております。
つボイ はい。患者さんにとっては低侵襲で、お医者さんにも患者さんにもメリットが大きいと言われております、このロボット支援手術。今後さらに広めていくにはどうしたらいいのでしょうか。
小高 このロボットもどんどん新しいものが出てきているようなんですね。そうすると、それを扱うことができるお医者さんの数も必要になりますし、そのお医者さん自身のスキルアップも重要になってきます。その辺の取り組みってどうなっているんでしょうか。岡田先生、よろしくお願いします。
つボイ はい。患者さんにとっては低侵襲で、お医者さんにも患者さんにもメリットが大きいと言われております、このロボット支援手術。今後さらに広めていくにはどうしたらいいのでしょうか。
小高 このロボットもどんどん新しいものが出てきているようなんですね。そうすると、それを扱うことができるお医者さんの数も必要になりますし、そのお医者さん自身のスキルアップも重要になってきます。その辺の取り組みってどうなっているんでしょうか。岡田先生、よろしくお願いします。
岡田 ロボットといっても、やっぱりあくまでロボット支援下手術ですので、それを扱える外科医がいなくては手術はできません。そこでロボットの各機種ごとにライセンスというものが必要になっています。
小高 ライセンス。
岡田 そのライセンスを取るために必要なトレーニングや施設、それを教える人材というのも必要になってきます。
つボイ ライセンスは車で言うと、普通自動車だったら車種を変えても乗れるんですけどに車種ごとにというか機種ごとに取るということですか。
岡田 そうですね。やはり各機種ごとにちょっと癖がありますので、そういう制度になっています。
小高 そのライセンスを取るために必要なトレーニングをしなければいけないとなると、そのトレーニング用の設備、それから教えてくれる人が必要になってくると。このトレーニングってどんなふうにやっていくんですか?
岡田 まずはオンラインなどで、その機種に関してしっかりと知識を得る。
小高 座学的な。
岡田 それから実際にロボットを使ったトレーニングですね。例えば鶏肉などの肉を使ったりとか、あとはテレビゲームのようなシミュレーターを使った訓練などもあります。
つボイ 自動車に例えてばっかりですけど、自動車学校なんかは1ヶ月くらい通ったりしますけど、どのくらいの期間が必要なんですか?
岡田 おおよそ1ヶ月くらいですね。
小高 トレーニングの設備もいるというお話でしたけれども、これはどこか病院とは別のトレーニング施設っていうのがあるんですか?
岡田 その企業の施設とかですね。最終的にそのライセンスを取れる場所は決まっていて、日本には2か所あります。東京とこの愛知だと藤田医科大学にその免許を取る施設があります。そこでまずロボットの機能とか操作を十分理解しているか問われた上で、実際に安全に動かせるかというのを監督されます。
つボイ 本当にいつも自動車学校に例えて申し訳ないんですが、やっぱり脱輪とかですね、どれか一回ダメでした!みたいなことはあるんでしょうか?
岡田 取れなかったっていうのはあまり聞いたことはないですね。でも人によってはかなり時間がかかった。終わる時間がかなり遅くなったという話は聞くことはありますね。
小高 私、自動車免許結構かかった。
つボイ かかってましたね~!(笑)お医者さんによってあるかもわかりませんね。
小高 そうすると、訓練を受ける側のお医者さんにとって必要なことってどんなことなんでしょう。
岡田 ロボットの機械の操作を覚えればそれだけでいいというわけではないです。
つボイ それでも操作自体も大変でしょう。
岡田 そうですね。操作自体も大変ですけど、例えば、高校生とかにやらせてもかなり飲み込みのいい子だったらすぐ動かしたりはできると思います。
小高 機械の操作だけの面においては。
岡田 そうなんですよね。それだけじゃなくて、やはり今までの腹腔鏡手術の経験であったり、当然ですけど解剖学的な、お腹の中がどういう構造になってるとか、そういう知識というのはもちろん必要になってきます。そして、医療機器というのは日々進化していますので、それにしっかり追いついていく、そういう対応能力が必要になってくると思います。
小高 その解剖学的な知識も、もともと外科医で手術されてきたお医者さんですから、持っていらっしゃると思うんですけれども、それからさらにロボット手術用の知識がいるということですか?
岡田 そうですね、それまでの知識というのが基になってくるとは思いますけど、やはりロボットを始めるにあたって、さらに細かい知識ということも要求されてくるかなと思いますね。
小高 ライセンス。
岡田 そのライセンスを取るために必要なトレーニングや施設、それを教える人材というのも必要になってきます。
つボイ ライセンスは車で言うと、普通自動車だったら車種を変えても乗れるんですけどに車種ごとにというか機種ごとに取るということですか。
岡田 そうですね。やはり各機種ごとにちょっと癖がありますので、そういう制度になっています。
小高 そのライセンスを取るために必要なトレーニングをしなければいけないとなると、そのトレーニング用の設備、それから教えてくれる人が必要になってくると。このトレーニングってどんなふうにやっていくんですか?
岡田 まずはオンラインなどで、その機種に関してしっかりと知識を得る。
小高 座学的な。
岡田 それから実際にロボットを使ったトレーニングですね。例えば鶏肉などの肉を使ったりとか、あとはテレビゲームのようなシミュレーターを使った訓練などもあります。
つボイ 自動車に例えてばっかりですけど、自動車学校なんかは1ヶ月くらい通ったりしますけど、どのくらいの期間が必要なんですか?
岡田 おおよそ1ヶ月くらいですね。
小高 トレーニングの設備もいるというお話でしたけれども、これはどこか病院とは別のトレーニング施設っていうのがあるんですか?
岡田 その企業の施設とかですね。最終的にそのライセンスを取れる場所は決まっていて、日本には2か所あります。東京とこの愛知だと藤田医科大学にその免許を取る施設があります。そこでまずロボットの機能とか操作を十分理解しているか問われた上で、実際に安全に動かせるかというのを監督されます。
つボイ 本当にいつも自動車学校に例えて申し訳ないんですが、やっぱり脱輪とかですね、どれか一回ダメでした!みたいなことはあるんでしょうか?
岡田 取れなかったっていうのはあまり聞いたことはないですね。でも人によってはかなり時間がかかった。終わる時間がかなり遅くなったという話は聞くことはありますね。
小高 私、自動車免許結構かかった。
つボイ かかってましたね~!(笑)お医者さんによってあるかもわかりませんね。
小高 そうすると、訓練を受ける側のお医者さんにとって必要なことってどんなことなんでしょう。
岡田 ロボットの機械の操作を覚えればそれだけでいいというわけではないです。
つボイ それでも操作自体も大変でしょう。
岡田 そうですね。操作自体も大変ですけど、例えば、高校生とかにやらせてもかなり飲み込みのいい子だったらすぐ動かしたりはできると思います。
小高 機械の操作だけの面においては。
岡田 そうなんですよね。それだけじゃなくて、やはり今までの腹腔鏡手術の経験であったり、当然ですけど解剖学的な、お腹の中がどういう構造になってるとか、そういう知識というのはもちろん必要になってきます。そして、医療機器というのは日々進化していますので、それにしっかり追いついていく、そういう対応能力が必要になってくると思います。
小高 その解剖学的な知識も、もともと外科医で手術されてきたお医者さんですから、持っていらっしゃると思うんですけれども、それからさらにロボット手術用の知識がいるということですか?
岡田 そうですね、それまでの知識というのが基になってくるとは思いますけど、やはりロボットを始めるにあたって、さらに細かい知識ということも要求されてくるかなと思いますね。
つボイ ロボットだけいくら進歩しても、それを扱うことができるお医者さんが増えなかったら宝の持ち腐れということになりますね。
小高 そのためにもトレーニング設備と教える人材が充実していくことが望まれるということだそうです。さあ、来週もロボット支援手術について岡田先生に教えていただきます。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
つボイ はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~ロボット支援手術~」でした。
小高 そのためにもトレーニング設備と教える人材が充実していくことが望まれるということだそうです。さあ、来週もロボット支援手術について岡田先生に教えていただきます。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
つボイ はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~ロボット支援手術~」でした。