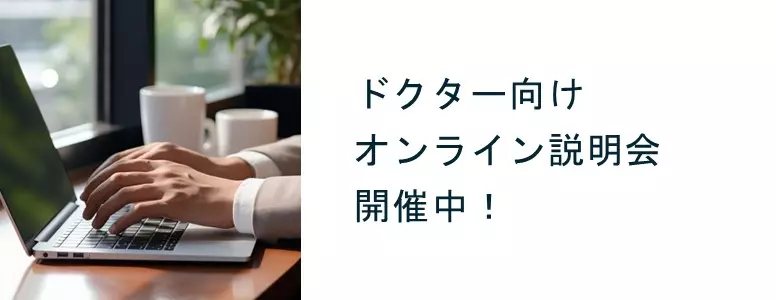第3回 ロボット支援手術の歴史と現状

小高 水曜日のこの時間は「健康のつボ!~ロボット支援手術について」、一宮西病院 外科副部長で消化器低侵襲手術センター副センター長の岡田 和幸先生に教えていただきます。
つボイ ロボット支援手術は低侵襲でメリットも多い手術法ということでしたけれども、いつ頃からこの手術の主流になってきたのかなというところ、気になりますよね。
小高 では、今日はそのロボット支援手術の歴史について、岡田先生に教えていただきます。
つボイ ロボット支援手術は低侵襲でメリットも多い手術法ということでしたけれども、いつ頃からこの手術の主流になってきたのかなというところ、気になりますよね。
小高 では、今日はそのロボット支援手術の歴史について、岡田先生に教えていただきます。
岡田 ロボット支援手術は、アメリカで1990年頃、戦場で傷ついた兵士をアメリカ本土や空母から医師が遠隔操作で手術するという発想のもと開発が進められました。
小高 あらま、軍事的な話から始まってるんだ。
岡田 最初はそうですね。それ以降、患者さんへの負担が少ない手術を可能にする手術支援システムとして、民間の方で開発が進められて、1999年に皆さんが聞かれたことがあるダビンチが完成しました。その後、2000年に腹腔鏡手術領域においてアメリカで承認が下りています。
つボイ はい。
岡田 それ以降、ロボット支援手術は技術面でも、医療現場における普及という面でも目覚ましい進歩をしております。ただ、日本ではその認可がなかなか下りず、世界に遅れをとっていました。
つボイ 下りなかった!
岡田 日本では、2009年に薬事承認を得まして、2012年にまずは前立腺がんの全摘手術が保険適用になりました。その後、保険適用がどんどん広がっていきまして、現在では胃がん、食道、直腸がん、肺がん、子宮がん、頭頸部がん、さらにがんではないんですが、心臓領域でも弁膜症に対する手術が保険適用となっています。
小高 思ったより早いですよね!
岡田 認可自体は遅れましたけど、そこからのスピードとしては早いですね。それぐらい有効なものであったんだと思います。
小高 期待もそうですし、有効であったということですね。
岡田 今では保険適用が広がったこともありまして、2024年では、世界でおよそ9000台ぐらいのダビンチというロボットが導入されている中で、日本では700台以上が保有されていまして、世界で第2位なんです。
つボイ この数字は頼もしいですね。
小高 それでも700台くらいだと、どの病院にも1台ありますって感じではないですよね。
岡田 やっぱりかなり高価なものになりますので、どの病院でもあるというものではないです。各都道府県に単純計算で20台もないということになりますね。
小高 ロボット支援手術というのは、最初のイメージだと限られた手術に使われてたような感じでしたけど、それも随分広がっているんですね。
岡田 ここ最近の話ですね。最初は前立腺、泌尿器科の方で手術が始まったんですけど、ここ数年で急速に手術数が増えていまして、保険適用になるとともに診療科もかなり増えてきています。
小高 岡田先生は、そのロボット支援手術でどんな手術を主にされているんでしょうか。
岡田 僕の専門は消化器外科、その中でも消化管、食べ物が通る道ですね。食道とか胃とか大腸で、主にそういった場所にできる悪性腫瘍、がんに対する手術を専門にしています。そちらに関してもロボット支援手術が保険適用になっています。
小高 ロボットでやったら、うわ!やりやすっ!とか思いましたか?
岡田 最初のイメージでは、腹腔鏡の手術で結構できてはいるという感覚はあったので、まあどうかなという思いはありました。実際にやってみると、やっぱり自分の手のような正確な動きができますので、かなりいいツールだと思っています。
小高 先生の病院では、このロボット支援手術というのはどのぐらいやってらっしゃるんですか?
岡田 今では年間100例ぐらいのロボット支援手術を当院ではさせてもらっています。
小高 最近だと、そのロボット支援手術もどんどん進化はしてるんでしょうか?
岡田 最新の機種になりますと、傷が1つで済みます。今までは4本が別々の穴から入っていたんですけど、1つの穴から4本ロボットの手が入って、その手がお腹の中でタコの足みたいにあちこちにぐにゅっと曲がる形でスペースを作って手術ができます。
小高 患者さんにとっては負担がどんどん少なくなりますね。
つボイ 穴が1つやからね。
小高 あらま、軍事的な話から始まってるんだ。
岡田 最初はそうですね。それ以降、患者さんへの負担が少ない手術を可能にする手術支援システムとして、民間の方で開発が進められて、1999年に皆さんが聞かれたことがあるダビンチが完成しました。その後、2000年に腹腔鏡手術領域においてアメリカで承認が下りています。
つボイ はい。
岡田 それ以降、ロボット支援手術は技術面でも、医療現場における普及という面でも目覚ましい進歩をしております。ただ、日本ではその認可がなかなか下りず、世界に遅れをとっていました。
つボイ 下りなかった!
岡田 日本では、2009年に薬事承認を得まして、2012年にまずは前立腺がんの全摘手術が保険適用になりました。その後、保険適用がどんどん広がっていきまして、現在では胃がん、食道、直腸がん、肺がん、子宮がん、頭頸部がん、さらにがんではないんですが、心臓領域でも弁膜症に対する手術が保険適用となっています。
小高 思ったより早いですよね!
岡田 認可自体は遅れましたけど、そこからのスピードとしては早いですね。それぐらい有効なものであったんだと思います。
小高 期待もそうですし、有効であったということですね。
岡田 今では保険適用が広がったこともありまして、2024年では、世界でおよそ9000台ぐらいのダビンチというロボットが導入されている中で、日本では700台以上が保有されていまして、世界で第2位なんです。
つボイ この数字は頼もしいですね。
小高 それでも700台くらいだと、どの病院にも1台ありますって感じではないですよね。
岡田 やっぱりかなり高価なものになりますので、どの病院でもあるというものではないです。各都道府県に単純計算で20台もないということになりますね。
小高 ロボット支援手術というのは、最初のイメージだと限られた手術に使われてたような感じでしたけど、それも随分広がっているんですね。
岡田 ここ最近の話ですね。最初は前立腺、泌尿器科の方で手術が始まったんですけど、ここ数年で急速に手術数が増えていまして、保険適用になるとともに診療科もかなり増えてきています。
小高 岡田先生は、そのロボット支援手術でどんな手術を主にされているんでしょうか。
岡田 僕の専門は消化器外科、その中でも消化管、食べ物が通る道ですね。食道とか胃とか大腸で、主にそういった場所にできる悪性腫瘍、がんに対する手術を専門にしています。そちらに関してもロボット支援手術が保険適用になっています。
小高 ロボットでやったら、うわ!やりやすっ!とか思いましたか?
岡田 最初のイメージでは、腹腔鏡の手術で結構できてはいるという感覚はあったので、まあどうかなという思いはありました。実際にやってみると、やっぱり自分の手のような正確な動きができますので、かなりいいツールだと思っています。
小高 先生の病院では、このロボット支援手術というのはどのぐらいやってらっしゃるんですか?
岡田 今では年間100例ぐらいのロボット支援手術を当院ではさせてもらっています。
小高 最近だと、そのロボット支援手術もどんどん進化はしてるんでしょうか?
岡田 最新の機種になりますと、傷が1つで済みます。今までは4本が別々の穴から入っていたんですけど、1つの穴から4本ロボットの手が入って、その手がお腹の中でタコの足みたいにあちこちにぐにゅっと曲がる形でスペースを作って手術ができます。
小高 患者さんにとっては負担がどんどん少なくなりますね。
つボイ 穴が1つやからね。
つボイ ロボット支援手術の発展のプロセスがよく分かりました。
小高 そうですね。日本は当初立ち遅れていたんですが、今では世界第2位の保有台数になっているとのことなんですね。まだまだどこの病院にでもあるという、そこまでの台数にはなってないんですけれども、導入している病院では、病気の種類によっては低侵襲の手術を受けることができるというわけですね。さあ、来週も岡田先生にロボット支援手術のことを教えていただきます。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
つボイ はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~ロボット支援手術~」でした。
小高 そうですね。日本は当初立ち遅れていたんですが、今では世界第2位の保有台数になっているとのことなんですね。まだまだどこの病院にでもあるという、そこまでの台数にはなってないんですけれども、導入している病院では、病気の種類によっては低侵襲の手術を受けることができるというわけですね。さあ、来週も岡田先生にロボット支援手術のことを教えていただきます。
そしてこのコーナー「健康のつボ!」では、いろいろな病気について専門家の先生に解説していただいております。みなさんもテーマとして取り上げてほしい病気や症状などがありましたら、このコーナーまでお寄せください。専門の先生に教えていただきます。
つボイ はい、質問お待ちいたしております!
小高 「健康のつボ!~ロボット支援手術~」でした。